パワハラ?部下に「仕事ができないやつだな」って言っても問題ない?

仕事のできは人によっても違うことでしょう。もちろん仕事ができる人は会社からの評価も高く、出世も早いことでしょう。ですが、全ての人が効率よく仕事ができるとは限りません。仕事ができなくて苦労をする人も少なくありません。そんな人の指導をしているとストレスにもなり、イライラからきつい口調で指導をしてしまうこともあるかもしれません。ですが、指導の方法を間違えてしまうことや、言葉一つでパワハラとして捉えられる可能性もあります。では「仕事ができないやつだな」言うとどうなってしまうのかを考えてみましょう。また、どのような指導や発言がパワハラになってしまうのかもあわせて、指導の方法について考えてみましょう。
パワハラの定義を理解しておくことが大切
まず、何がパワハラとなってしまうのかを指導者は理解しておくことが重要です。「パワハラをしているつもりはなかった」と思っているのは指導者側であり、その言動を相手がパワハラと受け取ってしまうこともあります。ではどのようなことがパワハラとなってしまうのかを紹介します。
パワハラの定義
職場におけるパワハラとは、①優越的な関係を背景とした言動であり、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、これら①~③の3つの要素をすべて満たすものをいいます。パワハラには「身体的侵害」「精神的侵害」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6つに分けられます。
身体的侵害
典型的なパワハラの一つともいえるもので、殴る・蹴る・突き飛ばすなど暴力や傷害の事です。
精神的侵害
脅迫や名誉棄損、侮辱、暴言などの精神的な嫌がらせを行う事で、こちらも典型的なパワハラと言えます。繰り返しこのような行為を受けることで精神障害を患ってしまうことも少なくありません。
人間関係からの切り離し
無視をする、仲間外れにする、別の部屋や離れた席で仕事をさせるなど、周囲から切り離すような行為です。孤立感を味あわせてしまい、こちらも精神障害となることもあります。
過大な要求
明らかに達成ができないようなノルマを課せることが良くある過大な要求のパワハラでしょう。また、達成できなかった仕事に対し、厳しく叱責するなどがあります。その他にも業務と関係ない仕事を押し付ける行為や、到底終わらない仕事を押し付ける行為などもこれにあたります。
過小な要求
こちらは過大な要求とは逆に、仕事をさせないことや、誰にでもできる程度の低い単調な作業をさせることがあげられます。
個の侵害
個とはその人のことで、プライベートなどプライバシーともいえる内容に過剰に踏み込む行為です。これは女性に対して行った場合、パワハラだけでなくセクハラにも当たる可能性があります。また、本人の了解を得ずに、他の人に個人情報を暴露する行為もこれにあたります。
指導をする上で3つの要素を理解し、これら6つのことに気を付けて指導をすることが重要です。また、ハラスメント行為を受けることで精神障害を患ってしまうことも少なくありません。
パワハラになるかもしれない言動には注意しておきましょう
指導をする立場の人は前述にあるような行為はパワハラになるということを十分に理解し、言動に注意する必要があります。指導をしていく上で、仕事の出来は人によって違いますので、成長速度もそれぞれ違いがあります。時にはうまく要領を得ることができず、先に進まない部下の指導をすることもあり、イライラすることもあるでしょうし、場合によっては叱ることも必要となる場面もあります。このような指導をする場合はパワハラとなることもありますので、以下の点に注意して指導を行うようにしましょう。
イライラをぶつける・嫌味を言う
部下のミスに対して、イライラしてしまうこともあるでしょう。ですが、その感情をそのままぶつけてしまうようなことはしないようにしましょう。また、嫌味に聞こえるようなことを言うなど、相手を委縮させてしまうような言動にも注意が必要です。これらの行為をすることで、部下は質問をしづらくなる上に、適切な報連相をも行うことができなくなることもあります。さらにそれが悪循環となりさらにイライラへとつながってしまう恐れもあります。
他の人の前で叱責や人格否定をする
他の同僚や部下がいる前で叱責することは、相手のプライドを傷つけてしまう可能性があり、仕事をミスしてしまうとまた怒られてしまうと思い、さらにミスにつながることもあります。また、その人の人格を否定するような発言はさらに精神的に追い詰めてしまう可能性がありますので言動には注意しましょう。
仕事を取り上げ、単調な仕事しかやらさない
仕事ができない部下に対し、仕事を取り上げることや、誰にでもできるような仕事しか与えないといった行為は仕事のモチベーションも下がり、簡単な作業ですらミスにつながってしまうことになります。さらに、ミスだけでなく、簡単な仕事ばかりですと、部下は成長できませんし、自分の必要性も感じることができず、自信を喪失させてしまうことになってしまいます。
指導を監視と間違えている
部下の指導にはつまずく部分で何がダメで、どのようにすれば良いのかなど、目標に向かっていくためのマネジメント能力が重要です。ですが、ミスをしないようにと常に監視をし続けるような行為は部下の集中力の妨げにもなり、ストレスを与えてしまうことになります。監視されていると、委縮してしまいさらにミスを誘発してしまうこともありますので注意しておきましょう。
「仕事ができないやつだな」ってパワハラになるの?
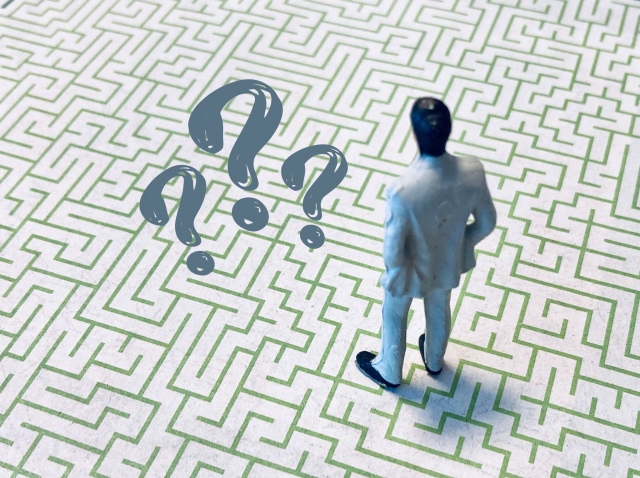
では、タイトルにもある「仕事ができないやつだな」といった発言はパワハラとなるのでしょうか。前項に記載しているものを振り返り、考えてみましょう。
そもそも仕事ができない人とはどのような人でしょうか?成績を上げることができない人でしょうか?それともミスばかり繰り返してしまうような人でしょうか?
仕事をする上でミスをすることは誰にも経験があるはずです。管理職の人でも、失敗をすることで成長してきたはずです。1回目のミスであれば昔の自分もそうだったと振り返り、再度指導をすることでしょう。2回目のミスでは「次は気を付けるように」と声をかけるのではないでしょうか。3回目では少し強めの口調になりながらも助言をすることでしょう。ですが、4回目ともなると、イライラも強くなり感情が爆発してしまうかもしれません。ですが、感情のままに言葉を言い放ってしまうことで「パワハラ」になってしまうかもしれません。さらにその暴言を他の従業員などがいる前でみせしめのように怒鳴りつける行為は悪質とも言え、パワハラだけでなく、名誉棄損に当たる可能性もあります。
仕事上でのミスをしてしまった部下に「仕事ができないやつだな」などと、乱暴な言葉で叱責することや罵倒することは、精神的に強くダメージを与えてしまうことになります。教育や指導とは仕事の基本や応用を教えていき、その目的を達成するために行うものです。仕事ができないからと感情的になり、怒鳴り声を上げることや罵声を浴びせてしまうことがないように注意するようにしましょう。
仕事ができない部下を指導するためのポイント
ここまでパワハラの定義やパワハラとなる可能性についてみていただきましたが、指導方法が業務上の範囲内だからパワハラにはならないだろうと思っていたこともあったのではないでしょうか。指導者側は指導と思い行っていたとしても、部下にとってはパワハラにあたる可能性があることを理解しておくことが重要です。では、部下に対してどのような指導をすればよいのかポイントを見ていきましょう。
なぜ「仕事ができない」のか問題点を把握する
仕事ができない部下は「なぜ上手く仕事をこなすことができないのか」を考えることが重要です。ただ単に「仕事ができない」とひとまとめにせず、「スキル不足」「経験不足」「やる気の問題」「プライベートなことで集中力が低下している」などどのような問題点があるのかを把握し、仕事ができない理由に対し、部下をサポートすることが指導者側には重要なポイントとなります。
細やかなサポートをする
仕事ができない理由にはスキル不足や知識不足、経験不足などがありますが、人には得意なことや不得意なことがあります。その人が一連の流れの中で、どの部分でつまずいているのかを把握しなければいけません。そのための方法として、業務の細分化がポイントとなります。細分化したものをステップごとに指導や助言を行うことで細やかなサポートをすることが可能になります。細分化した業務の区切りごとに、こまめに声掛けをし、進捗状況を確認し、適宜アドバイスを送るように声をかけることが指導のポイントとなります。
仕事ができない人とはコミュニケーションを取り、パワハラを回避する

部下に対して「仕事ができないやつだな」と言ってしまうことがパワハラにあたることをご理解いただけたかと思います。もし今までこのような指導をしていたのであれば、一度立ち止まり、どのような指導をしていけばよいのかを考えることが大切です。 部下がどのような状況で、仕事のどこでつまずいてしまっているのかを把握することと、それに対して細やかなサポートをすることが大切です。また、そのような人とはコミュニケーションをしっかりと取ることもパワハラを回避するためには重要です。仕事ができない人は躓いた時に上手く相談をすることができないこともあります。普段からしっかりとコミュニケーションを取っておくことで、つまずいた時や何か起きたときにでも、相談がしやすい関係性を作ることが大切です。さらに、上手くできたことや成長できた部分などに対しては褒めることも部下のモチベーションにつながり、仕事にも前向きになり成長にもつながります。また、普段からコミュニケーションを取ることはその人だけでなく、他の社員にも影響していき、パワハラが起きにくい組織へとなっていきます。普段からの行動や発言には注意し、パワハラにならないように気を付けるようにしましょう
