これってパワハラ?実は人によって境界線が異なります!
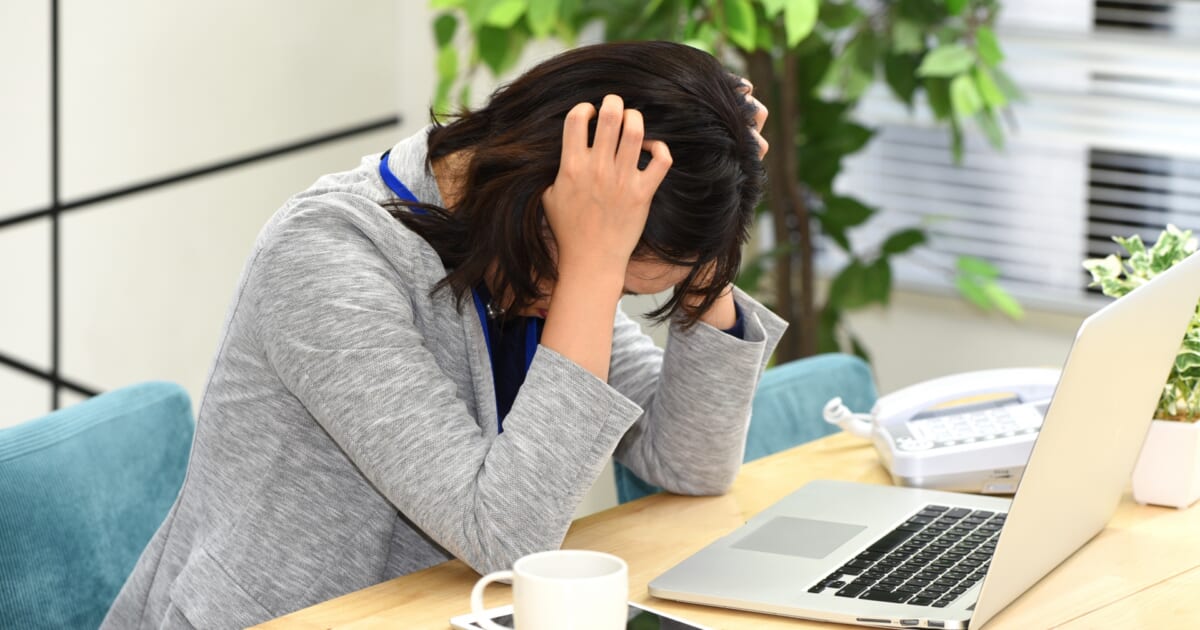
“パワハラ”と聞いて「私には関係ない」「そんなことをするわけがない」と思った方がいらっしゃるかもしれません。ですが「これはパワハラだ。」と感じる基準は人によって大きく異なっているのです。
自分自身は大丈夫と思っていても、実は周囲は苦痛を感じていた…なんてことも起こりえます。そんなことになる前に、パワハラについて詳しく知っておきましょう。
共通認識として知っておくべき!パワハラ認定の定義とは?
パワハラかどうかの判断は客観性が重要視されますので、定義は必ず知っておくことをおすすめします。
職場におけるパワハラについては「パワハラ防止法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)で定められています。
その中でパワハラ及び企業が講ずるべき措置について以下のように定義づけられています。
第30条の2
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
この条文は読み解くと3つの要素が含まれており、このすべてを満たすとパワハラに該当します。
- 優越的な関係に基づき行われる
- 業務の適正な範囲を超えて行われる
- 身体的・精神的な苦痛を与えること、就業環境が害されること
それぞれ細かく見ていきましょう。
1.優越的な関係に基づき行われる
・職務上地位が上位の者による言動
・同僚または部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
→業務を遂行するために、労働者が指示命令を拒否できない関係にあれば「優越的な関係」となります。
パワハラと聞くと一般的に上司から部下に対して行われるもの、というイメージが強いかと思いますが、同僚や部下からの行為であってもパワハラと判断される場合があるということです。
2.業務の適正な範囲を超えて行われる とは
・業務上明らかに必要性のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適当な言動
→明らかに業務上必要がないことを行わせることをさします。
3.身体的・精神的な苦痛を与えること、もしくは就業環境が害されること とは
・暴力による傷害
・暴言を吐くなど、人格を否定する行為
・何度も大声で怒鳴るなど、恐怖を感じさせる行為
・長期的に無視する、能力に見合わない業務を与え、就労意欲を低下させる行為
→労働者が身体的もしくは精神的に負担を感じ、業務の遂行に悪影響があることです。

6つに分けられる職場における代表的なパワハラ行為
職場におけるパワハラ行為は多種多様ですが、大きく6つの類型があるといわれています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
身体的な攻撃
<具体例>
殴る、蹴る、たたく、ものを投げつけるなど
→相手に直接的に暴力をふるう行為をさします。
精神的な攻撃
<具体例>
人格や能力を否定するような発言をする、怒鳴りつける、他の労働者の前で、大声など威圧的な叱責を繰り返し行うなど
→言葉による暴力をさします。
人間関係からの切り離し
<具体例>
気に入らない労働者に対し、業務を与えず長期間別室に隔離・自宅研修させる、一人の労働者に対し、集団で無視を行うなど
→孤立させるような行為をさします。
過大な要求
業務には関係のない私的な雑務を命じる、必要な教育を行わないまま到底実行できない業務を行わせ、実行できなかったことに対して叱責するなど
→相手の能力を超えた仕事を要求することをさします。
過小な要求
管理職である部下を退職させるため、だれでも遂行可能な事務作業を行わせる
気に入らない労働者に、仕事を与えないなど
→能力や経験に見合わない業務をさせることをさします。
個の侵害
職場内外で継続的に監視する、労働者の個人情報について本人の了承を得ず、他の労働者に伝えるなど
→職場の人のプライベートに過度に干渉するような行為をさします。
難しい「指導」と「パワハラ」の境界線…大きな違い7つのポイント
同じ行為でもパワハラと受け止めるか、指導として受け止めるかは相手の性格や普段からの関係性によって変わってきます。
そのため自分自身ではパワハラではないと思っている行為であっても、受け手によりパワハラと思われてしまうことが起こる、ということです。
誰もが納得する明確な境界線をひくことは非常に難しいですが、客観的に見て自分の行動がパワハラに当たるかどうか、判断しやすくなる大切なポイントがあります。
「パワーハラスメント防止ハンドブック」に基づき、指導とパワハラにおける大きな違い7つをご紹介します。
- 目的
- 業務上の必要性
- 態度
- タイミング
- 誰の利益なのか
- 自分の感情
- 結果
目的
指導は相手の成長を促すことが目的です。
それに対し、パワハラは相手を馬鹿にする、排除すること。また、自分の目的を達成させるために利用することが目的になります。
業務上の必要性
指導は職場の良い環境を保つために必要なことや、業務上必要性があることです。
対してパワハラは、業務上必要性のないこと(個人生活や人格を否定する)ことです。
態度
指導は肯定的、受容的、見守るといった態度です。
パワハラは威圧的、攻撃的、否定的、批判的といった態度です。
タイミング
指導はタイムリーにその場で、受け入れ体制が整っているときに行われます。
パワハラは過去のことを繰り返したり、相手の状況などを考えず突然行います。
誰の利益か
指導は組織も相手も利益があります。
パワハラは組織や自分(指示する人間)の利益が優先されます。
自分の感情
指導は穏やか、好意的な気持ちです。
パワハラはイライラ、怒り、嫌悪感があります。
結果
指導は部下が責任を持って発言、行動できます。職場に活気がある状態です。
パワハラのない職場とは?
パワハラは部下が委縮し、ぎすぎすした雰囲気であったり、退職者が増えてしまいがちになります。
これまでパワハラなんて関係ないと思っていた方も、パワハラと思われるのが怖くて指導しづらいと思っていた方も、常に自分の言動や行為を客観視し、前述のポイントを意識して指導を行うことで、受け手にパワハラと受け取られてしまうリスクは減らせます。
パワハラのない職場というのは、結果的に必要な指導が円滑に行われ、生産性が上がるメリットもあります。 今回ご紹介したポイントを今日からすぐに意識して実践し、身につけていきましょう。
