パワハラを会社に相談するのって、どういう方法があるでしょうか?

パワハラをはじめ、セクハラやモラハラと近年では様々なハラスメントが問題となっています。
上司や同僚から嫌がらせなどのパワハラを受けているけど、誰にも相談できずに困っている人も少なくないのではないでしょうか。
パワハラなどの被害を誰にも相談できないことが原因で仕事が手につかないだけでなく、うつ病などの精神疾患を患ってしまうこともあります。そうなる前にしっかりと相談をすることが大切です。ですが、「相談したことがバレ、さらにハラスメントが酷くならないか」など、ハラスメントがエスカレートしないかと悩む人もいらっしゃるでしょう。ですが、相談をしなければ何も解決はせず泣き寝入りをする羽目になるでしょう。
そこで、もしパワハラを受けた場合に相談できる窓口や、相談する際の準備や証拠など、どのようなものが必要となるのか、またパワハラの定義なども理解し、一人で悩まずに行動ができるようにしておきましょう。
社内でパワハラを受けていると感じたときに取るべき行動とは
もし社内でパワハラ被害を受けていると感じた際には一人で悩まず周りに相談することが大切です。
ではどのような行動をとると良いのかを見ていきましょう。
一人で悩まないで周りに相談しよう
パワハラなどのハラスメントを受けていると感じた場合は、我慢せずに周囲の人に相談をすることが大切です。ただ、相談する際に「あれはパワハラだ」「これもパワハラだ」などと騒ぐことはよくありませんが、我慢する必要はありません。
人は通常、ストレスや不安感が与えられるとそこから回避しようと抵抗をします。しかし、ハラスメントなどが常態化し、回避することができないようなストレス状態に置かれると、抵抗することをやめてしまう「学習性無力感」と言った自分でも気づかないうちに抵抗をすることを諦めやる気が失われてしまいます。そうするとさらに悪化してしまい、精神疾患を引き起こすこともあります。
また、パワハラを受けていることを放置していると相手の言動がエスカレートし、さらにハラスメント行為が悪化する恐れもあるため、状況が悪化する前に周囲に相談することが重要です。
パワハラの定義とは何かを知っておこう
上司からの言動を何でもかんでも「パワハラ」と捉えてはいけません。自分がパワハラを受けているかの判断は「パワハラの定義」を理解しておくことが大切です。ではパワハラの定義とはどのようなものなのでしょうか。
「職場のパワーハラスメント」とは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務上の適性を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を指します。パワハラと聞くと殴る蹴るなどの暴力や物を投げる、怒鳴り散らすなど攻撃的なイメージが強くありますが、それだけでなく、自分の能力に見合っていない無茶な仕事量を一人に押し付ける過大な要求や、仕事をさせない、簡単な作業だけを与える過小な要求などもパワハラとなります。
更に、無視をすることなどで周囲から孤立させる行動やプライベートの詮索などプライバシーの侵害もパワハラにあたります。
パワハラ6つの定義
・精神的な攻撃
・身体的な攻撃
・過大な要求
・過小な要求
・人間関係からの切り離し
・個の侵害
参照:パワハラ_6類型_厚労省
パワハラを受けていると感じたら一番身近な社内の相談窓口で相談できる
パワハラを受けていると感じたときに取るべき行動を見ていただきましたが、ではパワハラ被害に対して誰に相談すればよいのかと悩むこともあります。
一番身近なところとしては社内の相談窓口に相談することができます。
パワハラ防止法と呼ばれる「労働施策総合推進法」により、中小企業を含むすべての企業にはパワハラなどのハラスメントに対して相談ができるように相談窓口の設置が義務付けられています。
「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」として事業主は必ず講じなければならない具体的な措置があります。
・事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- 行為者について、厳正に対する旨の方針・対策の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
・職場におけるパワハラに関する事項の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
・合わせて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。
社内以外にもパワハラを相談できる相談窓口があることを知っておこう
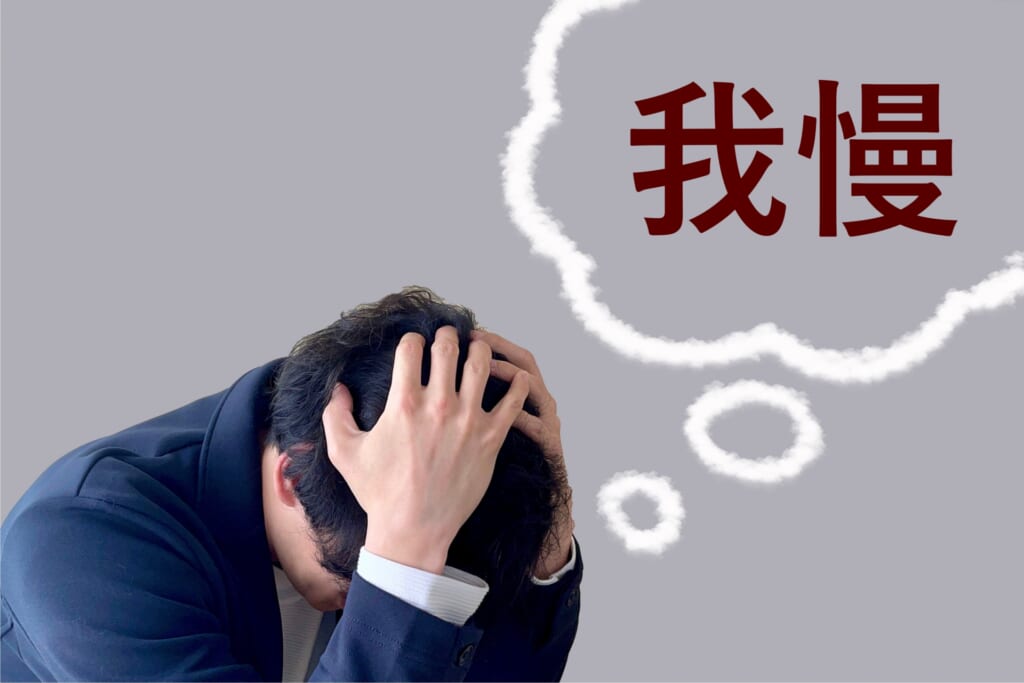
一番身近な相談窓口として社内の相談窓口について挙げておりますが、その他にも電話やインターネット等で相談ができる窓口があることを知っておきましょう。
総合労働相談コーナー
各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内など約380か所に設置されている相談窓口です。
総合労働相談センターは国が設けた相談窓口で、パワハラだけでなく、雇用や賃金などの労働についての問題も相談することができます。予約の必要性もなく無料で相談ができるだけでなく、電話での相談も可能です。
みんなの人権110番
パワハラ、差別、虐待など人権に関する問題について相談することができる機関です。こちらは法務局および各地方法務局に設置されています。
対面での相談はもちろん、電話やインターネットでの相談が無料ででき、対応してくれる人は法務局の職員または人権擁護委員ですので安心して相談することができる機関です。
労働相談ホットライン
労働相談ホットラインは、全国労働組合連合会(全労連)が設置している相談窓口で、労働者の立場に寄り添った対応をしてくれます。
こちらも無料で、電話やメールなどでパワハラ問題だけでなく、雇用などの労働に関する相談をすることができます。
パワハラの相談には事前準備が大切。相談する際に必要なものとは
パワハラを受けたと感じた場合に、相談することが大切とお伝えしましたが、相談をする際には正しい情報を伝えることが重要です。
正しい情報を伝えるためには事前に準備をしておくことが大切です。そこでどのような準備が必要かを確認しておきましょう。
パワハラの証拠
相談する際に必要となるものが「証拠」です。本人の証言だけでは「本当にパワハラがあったのか」「被害を大げさに言っていないか」など疑問が残る場合があります。証拠をもとに状況を正確に伝えることで、適切な対処をしてもらいやすくなります。
・暴言や人格否定などの音声データ
・パワハラに当たるメールやメッセージなどの文章
・被害の内容を記録した日記やメモ、ノートなど
・パワハラ被害により医療機関に受診した場合は病院の診断書
上記のような証拠は、客観的に証明することができるものとなりますので、準備しておくとよいでしょう。
経緯や状況を整理しておく
パワハラの証拠と共にパワハラ受けた経緯を時系列に沿って伝えられるように準備もしておきましょう。
・いつ、誰からどのようなパワハラを受けているのか
・パワハラが始まったと思われるきっかけ
・どのような頻度でパワハラを受けているのか
上記の状況などと併せて、「寝つきが悪くなった」、「出社前になると気分が悪くなる」など自分の心身の状況も記録して伝えられるようにしておきましょう。
パワハラから自分の身を守るためにも証拠はしっかりと集めておこう
前述にもあるようにパワハラの相談をする際には「証拠」が重要です。証拠を集める際にはデータで残すようにしておくと良いでしょう。具体的に三つを紹介していきます。
音声の録音や動画の録画
パワハラを証明するための最も強力かつ有力な証拠として「音声」「動画」が挙げられます。来られは裁判でも重要な証拠として認められるほどです。
スマホの録音機能や小型のICレコーダー、ボイスレコーダーなどを使い会話などの録音をするとよいでしょう。証拠を得るために会話の録音には許可を取る必要はありません。
しかし、これらのデータをSNSなどにアップロードすることは相手のプライバシーの侵害に当たる可能性がありますので、あくまで相談先に提出するためのものとして保管するようにしましょう。
チャットやメール、SNS投稿など
メールなどの文章も音声などのように証拠として重要なものとなります。送られてくるメッセージや相手が投稿するSNSなどで不快な思いをしたとしても削除やスルーをせずに残しておくようにしましょう。
また、保管できる期間が決まっているアプリや相手側から削除できるLINE、SNSなどは消される前にスクリーンショットを残すようにしておきましょう。
同僚や他の社員の証言
パワハラは他の人の前で行われることも少なくありません。同僚や他の社員の前でパワハラが行われていた場合は、目撃者の証言と本人の証言の整合性が取れれば証拠として認められる可能性があります。
目撃者がいた場合は協力を得ることができないか相談すると良いでしょう。ただ、加害者が事前に根回しをしている可能性もあり、協力を得ることができない場合もあります。そのような場合は、パワハラを目撃していた退職者などを頼ることも一つの手段です。
パワハラ被害を相談するためにもパワハラの証拠を集め自分を守ろう

仕事をしていると大なり小なり誰でもミスはします。しかし、必要以上の叱責や言動で責めることはパワハラとなります。
パワハラを受けていることを我慢・放置していると、気付かない間にどんどんと自分を苦しめてしまい、うつ病などの精神疾患を患ってしまうこともあります。
そうなる前に、パワハラの被害を受けていると感じた際は一人で抱えずに、周囲へ相談するようにしましょう。
大企業、中小企業関わらず、会社にはパワハラなどのハラスメントを防止するための相談場所が設けられています。ここで上げた音声データや文章などのデータなどパワハラの証拠をもって相談することで迅速に対応してくれることでしょう。
また、社内では加害者や周囲に知られるかもしれないと不安に感じる場合や適切な対処が施されなかった場合などには社外の相談窓口に相談をすることができることも覚えておくと良いでしょう。
