ストレス耐性のつけかた!失敗しても深く悩まないのがポイント?

「仕事がうまくいかずにイライラ」「職場での人間関係がうまくいかない」など人によってストレスの感じ方は様々です。このように職場でのストレスから仕事が手につかなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。
仕事をするうえで大なり小なりストレスはあります。できることであればストレスを感じることなく仕事をしたいですが、ストレスをゼロにすることはできませんので、耐性をつけることが一つのポイントとなります。
ここでは「ストレスの原因」「ストレスに弱い人・強い人の特徴」からどのようにして「ストレス耐性を高めることができるのか」を紹介します。
ストレス耐性について
ストレス耐性とは言葉通り「ストレスに耐えるための力」です。人間は仕事に関わらず、生活をするうえでさまざまなストレスを感じて生きています。そんなストレスにどれだけ対応できるか、耐えられるかが「ストレス耐性」です。
ストレス耐性が高い人ほど大きなストレスを受けても耐える、乗り越える力があります。反対に耐性が弱い人ほどちょっとしたことで落ち込むといった傾向があります。
このストレス耐性は意識して行動することや経験を積むことなどで高めていくことができますので「ストレス耐性の6つの要素」を理解し、行動することでストレス耐性を高めていきましょう。
ストレス耐性の6つの要素とは
1.感知能力
感知能力とは、原因となるストレスがある時にそれに気づくか気づかないかということです。そもそもストレスの原因に(例えば相手が言ったことが嫌味であっても)気づかなければストレスを感じることはありません。この「鈍感力」が重要なポイントとなりますが、これは個人の性格などによっても違いがあります。
2.回避能力
回避能力はそのままストレスを回避する能力があるかどうかです。ストレスを感じやすい、作りやすいかどうかがポイントです。仕事だからと割り切ることができるか、受け流すことができるかがこの能力の特徴です。この能力は自律神経系や内分泌系、免疫系の安定と関連性があるといわれています。心身が健康で安定していればストレスの影響は少なくなります。
3.処理能力
処理能力とはストレスの原因そのものをなくす、または弱めることができるかどうかの能力です。
ストレスの原因を上手に対処できるということはそのままストレスにも強いということが言えます。仕事量が多くストレスに感じている場合にどうすれば仕事量を減らすことができるのか、他の人にどう協力を仰ぐことができるかなど効率よく仕事をこなすことができるか調整できる力の事を言います。ストレスの原因となっている問題をその時の状況に応じて解決する力があることがポイントとなります。
4.転換能力
転換能力とは、ストレスを良い方向に捉え、置き換えることができるかどうかの能力です。
例えば「今回の失敗があったからこの問題に気づき学ぶことができた」「これをきっかけに、良い方向に変えていく」など、ポジティブに転換させる思考を持っているかどうかがストレス耐性の中でも重要なポイントとなります。
5.経験
経験とは、過去に受けたストレスの原因に対してどのように対応したかという経験値のことを言います。
何度も同じストレスに合うことで、そのストレスに慣れていき徐々にストレスを感じにくくなります。ですが、人によっては何度も同じストレスに合うことが逆にストレス耐性を弱めてしまうケースもあるので注意が必要です。
同じ失敗をしたときに「経験しているから大丈夫」と考えることができるか「また繰り返してしまった」と思うか経験を活かすことができるかどうかです。
6.容量
容量とはどれだけストレスを抱えることができるかどうかを言います。ストレスの抱えられる容量は人それぞれ違います。ストレスを抱えることができる許容範囲であればストレスと感じませんが、心に余裕がない場合や容量が小さい人の場合はストレスに耐えることも難しく、心身の問題の発生を起こしやすくなります。
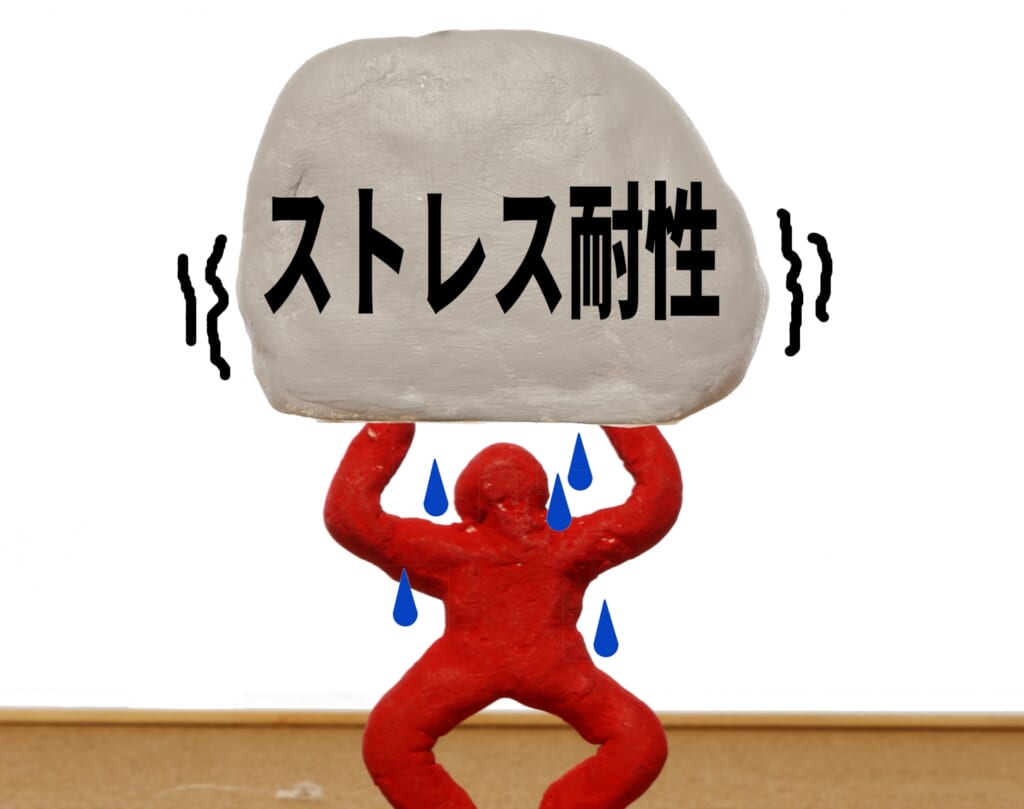
ストレス耐性は個人差、状況によっても違う
ストレス耐性の6つの要素を見てわかるように、ストレス耐性は個人の性格やストレスの捉え方によって差があります。
また同じ人でもその時の状況や状態などタイミングによって受ける大きさにも違いが出てきます。調子が良い時はストレスを受けてもあまり感じることがなかったとしても、失敗が続いているときや、体調が悪い時になると途端にストレスを抱えてしまうことになります。
自分自身のストレス耐性の高さや低さにとらわれず、どのようにすれば耐性を付けることができるのかを考える必要があります。
どのようにすればストレス耐性は付けられる?
ではどのようにすればストレス耐性を付けることができるかを見ていきましょう。
自分を知る
まず自分自身がどんなことによってストレスを感じるのかを理解しておくことが重要です。自分の性格、ストスの原因を認識できなければ改善するにもできません。
そのためにも自分の性格がどのようなものか、どんな時にストレスを感じ、ストレス反応を自覚することが必要です。ストレスの原因を客観的に判断できるようになることがストレス耐性をみにつけるためのポイントとなります。
目の前の事に集中する
人は常に考えることをしています。仕事ではもちろん、家庭内でも同じように様々なことを考え生活をしています。ストレスを受けたときにいろいろなことを考えているとそのストレスの解決方法を考えることができず、気づけば自分を追い込んでいるということにもなります。
今起きていることだけに集中して、客観的に物事を見る力を付けることで、そのストレスの原因を排除する方法を見つけ出すことができます。
過去の経験を活かす
ストレスを受けているとき、特に過度なストレスを受けているときは視野が狭くなるため受けているストレスのことしか考えることができません。
そんな時は過去に経験したつらかった、きつかった出来事を思い出し、どのようにして乗り越えることができたかを思い出してみましょう。
今まで経験してきたストレスが今より大きなものであったのであれば「過去に受けたストレスの方が大きく、今のストレスは小さい」と思え、少し楽な気持ちになれます。
もし、今のストレスの方が大きい場合であれば「これまでも乗り越えることができたので、今回も乗り越えることができる」と考えるようにしてみましょう。
このようにして過去の出来事を思い返し、大なり小なり乗り越えることができた経験が気持ちを前向きにしてくれます。
心を落ち着かせる
ストレスを受けるとどうしても周囲に雑音が気になり、不安も増幅してしまいます。そのようなときは楽な姿勢で目を閉じ、自分の呼吸に集中してみましょう。この時は物事を考えることをやめ「呼吸だけに意識」をしましょう。慣れないうちは数分で集中力が途切れ、他の事を考えてしまいますが、続けていることで集中力も増していきます。
この効果としてはストレスに対して考え込むことや、動揺することが減り、その結果ストレスに対して解決するための糸口を見つけ出すことに集中することができます。
ストレス以外にもこれを続けていくことによって集中力が増し仕事のパフォーマンス向上や生活習慣の改善、精神的な疲労改善にもつながります。
ストレスとの向き合い方こそが重要です
これらの事を意識しておくことでストレス耐性が身につき、ストレスに強くなっていきます。 「何で失敗したのだろう」「自分はだめな奴だな」と深く考えすぎるのではなく、例え失敗をしたとしても「今の自分(心身)はどのような状況なのか」「以前はどのようにして乗り越えたのか」「心を落ち着かせながら整理する」ことでストレスと向き合いことができ、前向きな考え方へと変わっていきます。
